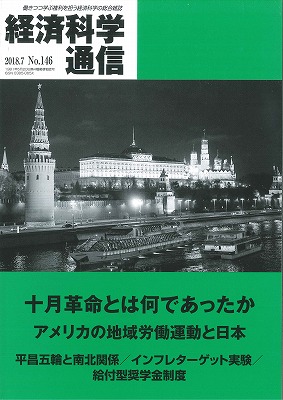【日 程】2019年3月16日(土)-17日(日) 午前・分科会、午後・共通セッション 【場 所】横浜国立大学 経済学部棟 【資料代】2000円 (学生等 1000円) *事前申込不要・一般参加歓迎 【懇親会】4000円(要予約) 【共通セッションテーマ】 共通セッション1(3月16日) テーマ:「アジアにおける格差の拡大と中間層の解体」 報告者:明石博行(駒澤大学)、大西広(慶應義塾大学)、和田幸子(元・神戸外国語大学) 共通セッション2(3月17日) テーマ:「ラテンアメリカの激動とアジアの格差・中間層問題」 報告者:所康広(明治大学)、山崎圭一(横浜国立大学)、クラウディオ・モンゾン(駐日キューバ共和国大使館) . . . → Read More: 2019年春季研究交流集会横浜国立大学)開催のご案内
|
||||
|
日時:3月3日(日)午後14:00時~17:00時 場所:キャンパスプラザ京都 6F 第一講習室 プログラム 報告1:山田博文(群馬大学名誉教授)「「現代日本の財政ファイナンスと日銀トレード」 報告2:河音琢郎(立命館大学経済学部)「ポスト・リセッションのアメリカ財政政策とFRBの金融政策」 コメンテーター:大畑智史(三重短期大学) 資料代:500円 *事前申込不要 . . . → Read More: (3月3日)現代資本主義研究会(共催:立命館大学経済学会セミナーシリーズ)のご案内 基礎研では創立50周年記念事業の一環として2008年の『時代はまるで資本論』の全面改訂版の出版を企画しています。出版に先立って執筆者会議を公開研究会として東京と京都で開催することになりました。東京では1月27日に研究会を開催し、京都での公開研究会について次の日程で開催します。ご関心のある方はご参加ください。 【日 時】:1月19日(土)13;30-17:30
. . . → Read More: (京都)『時代はまるで資本論』改訂版のための研究会のご案内 日時:2018年12月8日(土)午後14時~17時
会場:立命館大学朱雀キャンパス:2F202教室
※玄関入って右側エレベーターで2階へあがって下さい
報告:藤田実(桜美林大学教授・所員)「『戦後日本の労使関係』の執筆意図と主な論点について」
コメンテーター:高田好章(所員)「『戦後日本の労使関係』の労働学科における輪読・議論から」
司会;笠井弘子(所員)
. . . → Read More: (12月8日)現代資本主義研究会「戦後の労使関係を論じる」のご案内 基礎経済科学研究所は創立50周年を記念して『資本論』入門書の改定版の編集を始めていますが、それをよりよいものとするために研究会を東西それぞれで開催することとなりました。そして、そのために「東」の東京支部としては以下のように3方のご報告をいただくこととなりました。全体編集責任者の小沢修司先生も来られますので、皆様の積極的な討論への参加を期待します。
日時 2019年1月27日(日)14:00-17:30
資料代:500円
会場 慶應義塾大学三田校舎研究棟A会議室
報告1 後藤康夫(福島大学名誉教授)「21世紀の世界と人間解放論としての『資本論』」
報告2 平松民平(基礎研所員)「AI化、NET革命下での情報と労働 」
報告3 加藤光一(松山大学教授)・三木敦朗(信州大学助教)「エコロジーと物質代謝〜地代論の可能性〜(仮)」
. . . → Read More: (東京支部)『時代はまるで「資本論」』改定版 のための支部研究会のご案内 日 時:11月3日(土・文化の日)AM9:30~PM5:30
資料代500円 (終了後、懇親会を予定しています)
会 場:専修大学神田校舎(千代田区神田神保町3丁目8)(午前・午後とも)5号館542
テーマ:
(A)労働組合の組織拡大の先進事例
(B)戦後労働運動の転機と克服課題
論 点:産別会議はなぜ崩壊し、伝統を継承できなかったか。企業内組合の歴史的生成はどのように進んだか。労使協調の潮流はどのように成長したか。総評労働運動の功罪は。日本労働運動の労使関係の弱点と克服課題は何か。労働組合組織強化の先進事例、など。
. . . → Read More: (東京支部研究集会)『労働組合運動の転機と展望』(第1回)のご案内 . . . → Read More: 経済科学通信146号発行のお知らせ 当現資研は7月7日に予定でしたが、6月18日朝、M6.1の大阪北部地震のために会場変更、さらに直前の7月5日からの西日本豪雨のため大学休講により前日に中止(延期)となりました。曰く「踏んだり蹴ったり」の開催となり、自然災害とはいえ皆様にご心配・ご迷惑をおかけいたしました。改めて10月6日に行います。
接客労働、医療・介護労働や様々なサービス労働を対象に、「感情労働」あるいは「ケア労働」と呼ばれる働き方が広がり、その理論的な問題提起がなされてきました。感情労働論は、ブレイヴァマンの労働過程論研究に依拠したホックシールドが、旅客機客室乗務員の調査を元に接客サービス分析により始まりました。感情が企業の営利目的に従属され、接客における他人への感情変化・雇主による感情管理の問題提起に対し、様々な論者からの批判と反批判を巻き起こす論争が行われてきました。サービス産業の広がりとともに、感情労働論は重要な問題ですが、日本では議論の広がりがまだまだ少ないと思われます。 今回の現資研では、最初に青木圭介さんから、感情労働論の様々な理論的な問題提起とその流れを整理していただきます。続いて、福祉施設・介護施設・医療現場で働いている労働者が、現場でどの様な働き方・問題が起こっているのかを、労働組合の立場から現場の状況をよくご存じの南守さんに具体的に語っていただきます。さらに、救急隊の労働について、現場で働いておられる子島喜久さんにその実態を話しとともに、研究者としての立場からも感情労働論への理論的問いかけをしていただきます。 「働き方改革」で働き方・働かせ方をめぐる議論が多く語られる今、基礎研がこれまで積み上げてきた労働過程論に、感情労働論を軸にさらに一石を投じる議論を展開します。ぜひご参加ください。
日時:2018年10月6日(土)午後2時~5時
会場:立命館大学朱雀キャンパス:2F202教室(JR・京都地下鉄二条駅下車徒歩2分) ※玄関入って右側エレベーターで2階へあがって下さい 報告:
青木圭介(所員・京都橘大学名誉教授)「分業論と感情労働」
南 守(福祉・介護・医療労働者組合執行委員長)「ケア労働とはどんな働き方か」 子島喜久(所員・東京支部)「救急隊の労働・コメディカルスタッフと感情統制」 司会:
高田好章(所員)
. . . → Read More: 現代資本主義研究会 「感情労働論・ケア労働をめぐって」(7月7日順延分) 今回の半島非核化への平和的合意の実現には韓国の文在寅大統領や中国の習近平主席が大きな役割を果たしました。アメリカのトランプ大統領も役割を果たしましたが、日本外交は最後まで圧力一辺倒の外交でこの転換に一切何の役割も果たしませんでした。これは「日本外交の失敗」で、今後は北東アジアの大勢に取り残される恐れがあります。この問題を今回のシンポジウムでは国際関係論的な視角から議論します。また、今後求められる在韓米軍の縮小・撤退に関わる現地調査の報告も行われます。
日時:10月7日(日) 2:00-5:00 場所:慶應義塾大学三田校舎研究室棟A会議室 資料代:500円 *一般参加歓迎・事前申込不要 報告1:大西広(慶應義塾大学教授、北東アジア学会前会長)「国際関係論から見た北東アジアの転換」 報告2:中瀬勝義(基礎研所員)「在韓米軍の現在と韓国の反基地闘争」
会場:立命館大学朱雀キャンパス 日程:2018年8月25日(土)-26日(日) 資料代:2000円 *事前申込不要・一般参加歓迎
時間:第一日目(8月25日(土)) 9:30-17:45 (創立記念パーティー 18:00ー20:00) 第二日目(8月26日(日)) 9:00-16:00 (総会 16:00-17:00)
. . . → Read More: 創立50周年記念大会開催のお知らせ |
||||